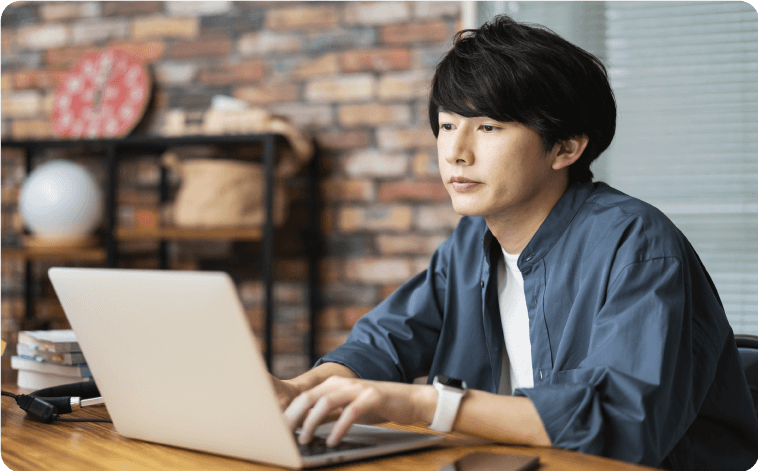院長コラム
ヘバーデン結節 と へパーデン結節 どちらが正しい? 病名の由来について
2025.05.12
ヘバーデン結節とブシャール結節
整形外科の疾患
長野市若穂は葉桜に変わり、新緑の美しい季節になりました。
さて今回のコラムは、病名に関する雑学について。
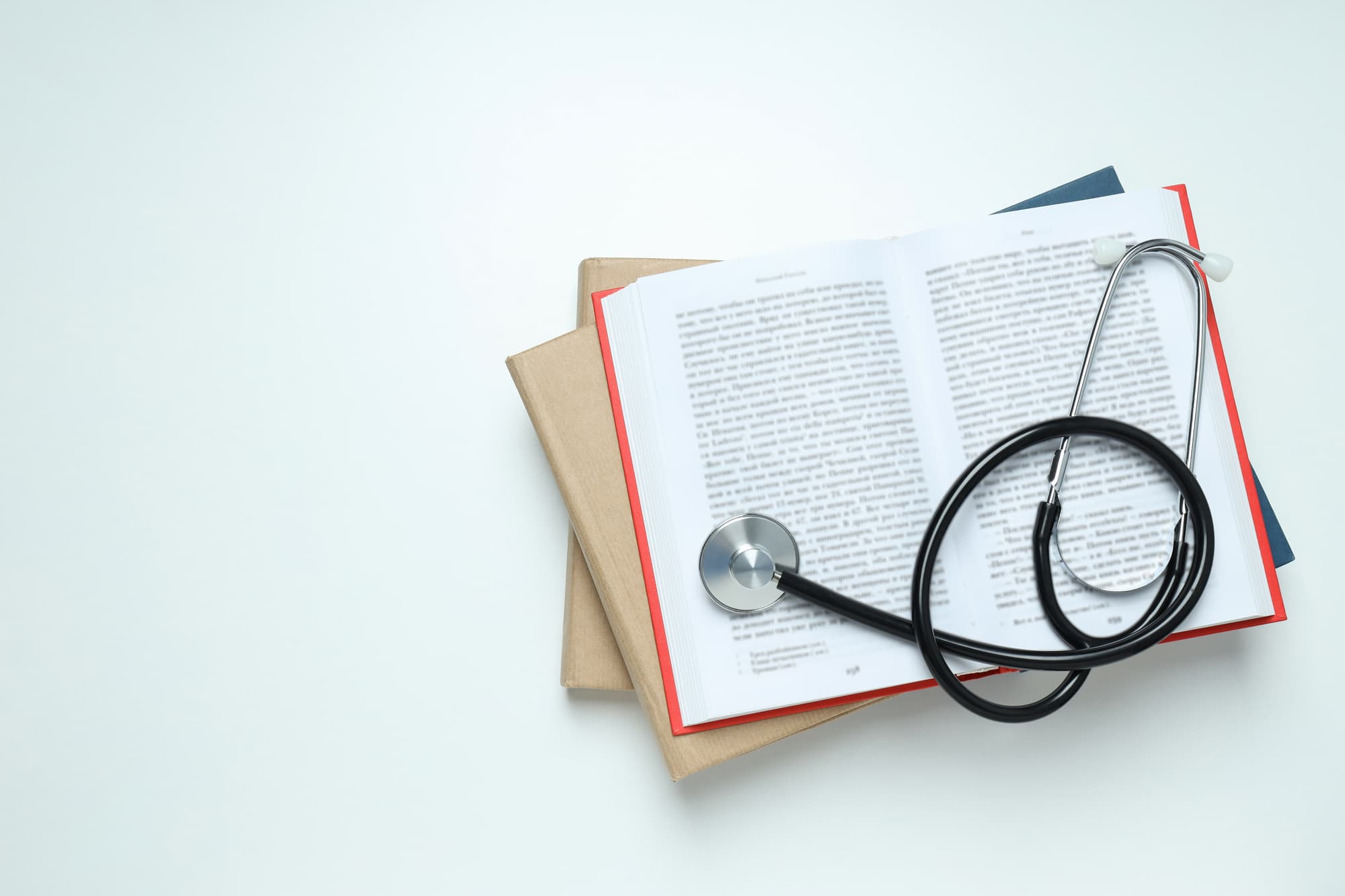
当院を受診する患者さんのなかには、時々「へパーデン結節」と発音される方がいますが、コレ正しくは「ヘバーデン結節」です(へパーデンのほうが言いやすいのかな?)。
医学において病名はしばしば発見者にちなんで名付けられますが、ヘバーデン結節(Heberden’s node)も、イギリス人の医師・ウィリアム・ヘバーデン(William Heberden, 1710 – 1801)の名前に由来しています。
ヘバーデン氏はケンブリッジ大学で医学博士号を取得した後、ロンドンで内科医として診療を行いながら論文を発表しました。
彼は「狭心症(Angina pectoris)」の命名者としても知られています。
ちなみに、第二関節に起こる変形性関節症「ブシャール結節(Bouchard’s nodes)」も、同じようにフランスの病理学者・チャールズ・ジャック・ブシャール(Charles Jacques Bouchard, 1837 – 1915)が発見したことで名付けられました。
すでに18世紀と19世紀にそれぞれの病気が発見されていたわけですが、長年にわたって「原因不明、治療は対症療法」とされてきました。
いまでは、ヘバーデン結節とブシャール結節は「治せる病気」になりました。
早期発見と根本治療で、指の変形を防ぎましょう。